長い干ばつの後、星のような雨が降り注ぎ、少年は走りながら恵みの雨に歓声を上げた。
雨は長い間降り続け、キャラバンは緑に覆われた大地にしばし腰を下ろす。
「お母さん、お姉ちゃん、これでもうお腹が減ったり、寒くなったりしないね!」
エヴィキン人の焚火が長い夜を温める中、少年は姉の物語を聞きながら夜明けを待っていた。
「カカワーシャ、あなたはお母さんから授かった幸運をもって、私たちにできなかったことを成し遂げて…あなたの旅がいつまでも平穏で、その計略が決して露見しませんように……」
金色の陽光が夢の中から現実の住まいへと差し込み、再び取引と数字が目に飛び込んでくる。
彼は握りしめていた手を静かに緩めた——
何も掴めなかったように開かれたそこには、まだ微かなぬくもりが残っていた。
雨は長い間降り続け、キャラバンは緑に覆われた大地にしばし腰を下ろす。
「お母さん、お姉ちゃん、これでもうお腹が減ったり、寒くなったりしないね!」
エヴィキン人の焚火が長い夜を温める中、少年は姉の物語を聞きながら夜明けを待っていた。
「カカワーシャ、あなたはお母さんから授かった幸運をもって、私たちにできなかったことを成し遂げて…あなたの旅がいつまでも平穏で、その計略が決して露見しませんように……」
金色の陽光が夢の中から現実の住まいへと差し込み、再び取引と数字が目に飛び込んでくる。
彼は握りしめていた手を静かに緩めた——
何も掴めなかったように開かれたそこには、まだ微かなぬくもりが残っていた。
旅が平穏であるように

 存護
存護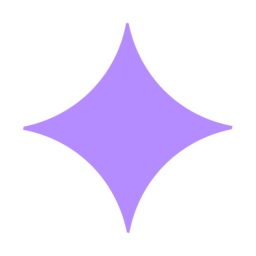
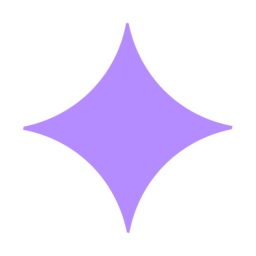
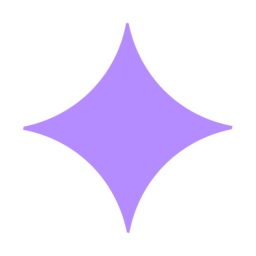
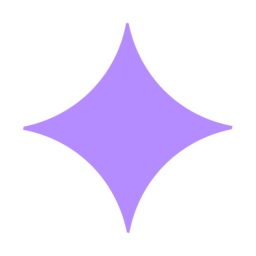
Lv.1/20
 HP
HP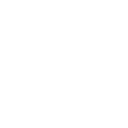 攻撃力
攻撃力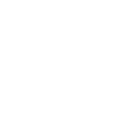 防御力
防御力






 Add to Planner
Add to Planner甘い夢
装備��キャラが付与するバリアの耐久値+12% 。味方がバリアを持つ時、与ダメージ+12% 。
長い干ばつの後、星のような雨が降り注ぎ、少年は走りながら恵みの雨に歓声を上げた。
雨は長い間降り続け、キャラバンは緑に覆われた大地にしばし腰を下ろす。
「お母さん、お姉ちゃん、これでもうお腹が減ったり、寒くなったりしないね!」
エヴィキン人の焚火が長い夜を温める中、少年は姉の物語を聞きながら夜明けを待っていた。
「カカワーシャ、あなたはお母さんから授かった幸運をもって、私たちにできなかったことを成し遂げて…あなたの旅がいつまでも平穏で、その計略が決して露見しませんように……」
金色の陽光が夢の中から現実の住まいへと差し込み、再び取引と数字が目に飛び込んでくる。
彼は握りしめていた手を静かに緩めた——
何も掴めなかったように開かれたそこには、まだ微かなぬくもりが残っていた。
雨は長い間降り続け、キャラバンは緑に覆われた大地にしばし腰を下ろす。
「お母さん、お姉ちゃん、これでもうお腹が減ったり、寒くなったりしないね!」
エヴィキン人の焚火が長い夜を温める中、少年は姉の物語を聞きながら夜明けを待っていた。
「カカワーシャ、あなたはお母さんから授かった幸運をもって、私たちにできなかったことを成し遂げて…あなたの旅がいつまでも平穏で、その計略が決して露見しませんように……」
金色の陽光が夢の中から現実の住まいへと差し込み、再び取引と数字が目に飛び込んでくる。
彼は握りしめていた手を静かに緩めた——
何も掴めなかったように開かれたそこには、まだ微かなぬくもりが残っていた。
