「へえ、本当にそれでいいの?」
「フン、絶対に間違いないわ!」
「今回の賭けは、手用軟膏1本だけじゃないから��ね」
「こんな単純な遊びに…変数があるわけないもの」
桃色の髪の少女は顔を背け、それ以上惑わされないようにした。
「茶柱の立ち具合から察するに、君はあれを出すべきだと思うけど」
女性は札を引き、裏返した——
「あら、ツキが回ってきたみたい」
「もう1回!こんなのあり得ない……」
……
少女は姉弟子とどれほどの回数、占い遊びをしたか忘れてしまった。ただ覚えているのは、姉弟子がいつも「もう1回」に付き合ってくれたことだけ。
その後、定められた予言から逃れようと、少女は反対を押し切って羅浮の太卜司に入った。
羅浮に着いたばかりの頃、彼女は本に1枚の綺麗なくじ札が挟まっているのを見つけた。異郷の地で目にしたよく知る筆跡に、少女の目元がじわりと熱くなった。
「運命に別の可能性がないなんて誰が決めたの?私の幸運のくじを、君にあげる」
「フン、絶対に間違いないわ!」
「今回の賭けは、手用軟膏1本だけじゃないから��ね」
「こんな単純な遊びに…変数があるわけないもの」
桃色の髪の少女は顔を背け、それ以上惑わされないようにした。
「茶柱の立ち具合から察するに、君はあれを出すべきだと思うけど」
女性は札を引き、裏返した——
「あら、ツキが回ってきたみたい」
「もう1回!こんなのあり得ない……」
……
少女は姉弟子とどれほどの回数、占い遊びをしたか忘れてしまった。ただ覚えているのは、姉弟子がいつも「もう1回」に付き合ってくれたことだけ。
その後、定められた予言から逃れようと、少女は反対を押し切って羅浮の太卜司に入った。
羅浮に着いたばかりの頃、彼女は本に1枚の綺麗なくじ札が挟まっているのを見つけた。異郷の地で目にしたよく知る筆跡に、少女の目元がじわりと熱くなった。
「運命に別の可能性がないなんて誰が決めたの?私の幸運のくじを、君にあげる」
今日は好運

 愉悦
愉悦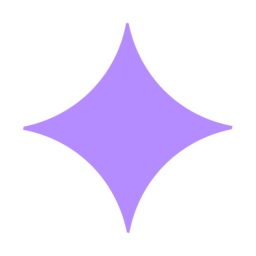
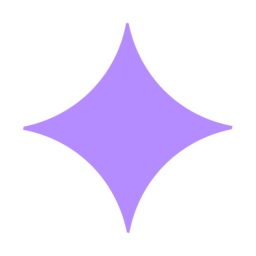
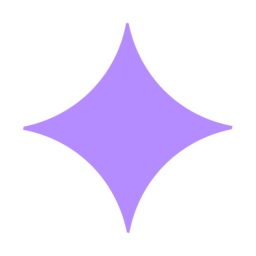
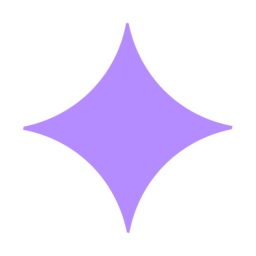
Lv.1/20
 HP
HP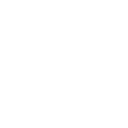 攻撃力
攻撃力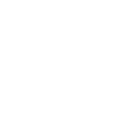 防御力
防御力






 Add to Planner
Add to Planner選択
装備キャラの会心率+12% 。装備キャラが愉悦スキルを発動する時、愉悦度+12% 、この効果は最大で2 回累積できる。
「へえ、本当にそれでいいの?」
「フン、絶対に間違いないわ!」
「今回の賭けは、手用軟膏1本だけじゃないからね」
「こんな単純な遊びに…変数があるわけないもの」
桃色の髪の少女は顔を背け、それ以上惑わされないようにした。
「茶柱の立ち具合から察するに、君はあれを出すべきだと思うけど」
女性は札を引き、裏返した——
「あら、ツキが回ってきたみたい」
「もう1回!こんなのあり得ない……」
……
少女は姉弟子とどれほどの回数、占い遊びをしたか忘れてしまった。ただ覚えているのは、姉弟子がいつも「もう1回」に付き合ってくれたことだけ。
その後、定められた予言から逃れようと、少女は反対を押し切って羅浮の太卜司に入った。
羅浮に着いたばかりの頃、彼女は本に1枚の綺麗なくじ札が挟まっているのを見つけた。異郷の地で目にしたよく知る筆跡に、少女の目元がじわりと熱くなった。
「運命に別の可能性がないなんて誰が決めたの?私の幸運のくじを、君にあげる」
「フン、絶対に間違いないわ!」
「今回の賭けは、手用軟膏1本だけじゃないからね」
「こんな単純な遊びに…変数があるわけないもの」
桃色の髪の少女は顔を背け、それ以上惑わされないようにした。
「茶柱の立ち具合から察するに、君はあれを出すべきだと思うけど」
女性は札を引き、裏返した——
「あら、ツキが回ってきたみたい」
「もう1回!こんなのあり得ない……」
……
少女は姉弟子とどれほどの回数、占い遊びをしたか忘れてしまった。ただ覚えているのは、姉弟子がいつも「もう1回」に付き合ってくれたことだけ。
その後、定められた予言から逃れようと、少女は反対を押し切って羅浮の太卜司に入った。
羅浮に着いたばかりの頃、彼女は本に1枚の綺麗なくじ札が挟まっているのを見つけた。異郷の地で目にしたよく知る筆跡に、少女の目元がじわりと熱くなった。
「運命に別の可能性がないなんて誰が決めたの?私の幸運のくじを、君にあげる」
